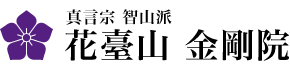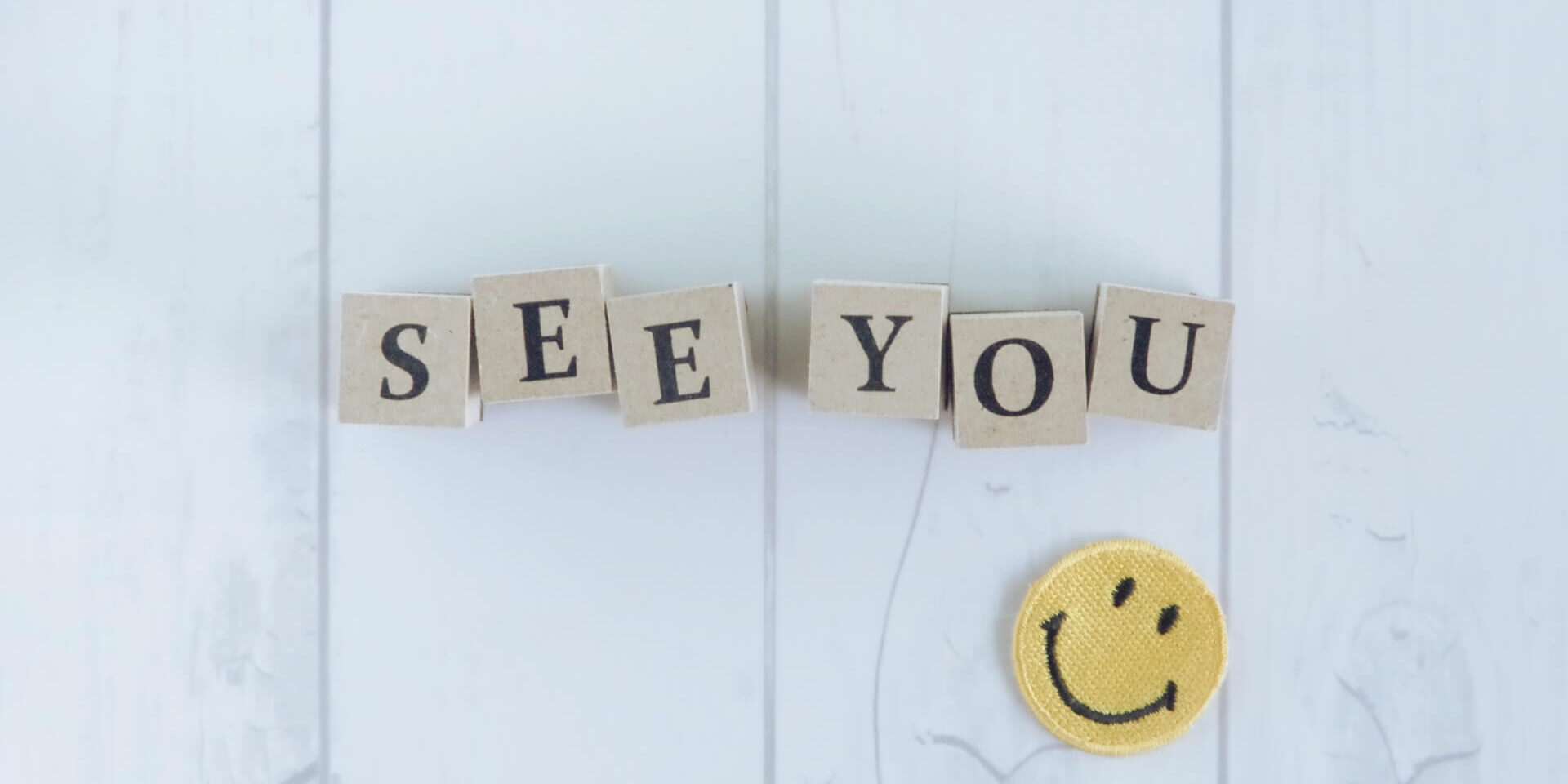私が京都で修行をしていた時に「どうしたら話が上手になりますか?」と先生に尋ねたことがございます。
すると先生から「落語を聞くといいよ。」と教えて頂きました。
私はそれから落語を聞くようになり、『松山鏡』という演目に出会いました。
この話は越後にある【鏡というものを知らない村】が舞台になっています。
話は以下のような内容です。
越後のあるところに、誰も【鏡】というものを知らない村がありました。
この村には、両親を早くに亡くし、18年間毎日欠かさず墓参りをしていた男がおりました。
両親を想い熱心にお墓参りをする男の姿が、やがてお上の目にとまり、褒美を頂けることになりました。
お上:「何か欲しいものはないか?」
男:「いいえ、何もありません。」
お上:「本当にないのか?どんなことでも遠慮せずに言っていいんだぞ?」
しばらく考えて、男はこう言いました。
男:「18年前に亡くなった私の父に会いたいです。たとえ夢でもいいから父にもう一度会いたいのです。」
お上:「・・・そうか、わかった。ところで、お前は誰かに【父親とそっくりだ】と言われたことがあるか?」
男:「はい、よく言われます。」
男の返事を聞いたお上は、そばにいた家来に向かって、
お上:「その箱の中にある【鏡】を取ってくれないか?」
家来:「はい、こちらですね?どうぞ。」
家来から【鏡】を受け取ると、
お上:「これは【鏡】というものだ。これをお前にやろう。ほら、見てみなさい。」
と男に【鏡】を手渡しました。
【鏡】を手にして、中を覗き見た男は泣いて喜びました。
男:「ここに父がいる!!やっと会えた!!!」
男の父親は45歳で他界をしており、男は亡き父と同じくらいの年齢になっていました。
そして、亡き父とよく似ていた男は、鏡に映る自分の顔を【父の顔】だと思ったのです。
お上は【鏡】を渡す際に、『子は親に似たるものをぞ亡き人の恋しきときは鏡をぞ見よ』と歌を添えました。
そして、男に向かってさらにこう注意をしました。
お上:「この【鏡】は決して他の誰にも見せてはならんぞ。おまえの妻にもだ、よいか?」
男:「はい、誰にも見せません。」
男は【鏡】を家に持って帰り、嬉しさのあまり妻に内緒で毎晩のように見ていました。
しかし、女性というのは観察眼が非常に優れていますので、夫の不審な行動にはすぐ気がつきます。
男が留守中に【鏡】を見つけ出し、中を覗いてみると、そこには女性の顔が映っているわけです。
それがまさか自分の顔だとは知らない妻、帰宅してきた夫に激しく詰め寄りました。
妻:「ちょっとあなた!他に女がいるんじゃないの!?あなたが毎晩ニヤニヤしながら会っている女は誰なのよ!!」
男:「えっ、女?一体何を言っているんだ!?そんなのは知らん!!」
妻:「ウソを言うんじゃないわよ!!!あなたが毎晩ニヤニヤして見ているモノの中に女がいたのよ!!!!!」
男:「だーーかーーらーー!!そんな女は知らんと言っているだろうが!!!」
妻:「はぁ~っ!?じゃあ、何よ??私の方がウソを言っているとでも!?」
そんなやりとりを、ちょうどそばを通りかかった尼僧さんが見ていて、あわてて仲裁に入りました。
尼僧さん:「ちょっとちょっと、そんなにケンカをして、一体どうしたのよ?」
男と妻は、仲裁に入った尼僧さんへケンカの経緯を説明しました。
尼僧さん:「あなた達が見ていたモノをここへ持ってきなさい。私が確かめてあげるから。」
男は家の奥から【鏡】を持ってきて尼僧さんに渡しました。
【鏡】を覗きこんだ尼僧さんはニッコリ笑って言いました。
尼僧さん:「ねぇ奥さん、もう許してあげたらどう?だって、ここにいる女性はとても反省して頭を丸めているわよ。」
この話、私は個人的に好きなのですが、いかがでしょうか?
もし気になる方は、寄席やネットで実際に落語家さんのお話を聞いてみてください。
今も昔も亡くなった人に【夢でもいいから会いたい】と思うのは同じなのですね。
仏教には『浄土』と呼ばれる世界があり、私たちは亡くなった人と『浄土』で再び出会えると説かれています。
亡くなった方は先に旅立たれましたが、私たちもいつかは行く世界です。
無常の世だからこそ、大切な人ともう一度出会えると思うと何だか心強いですよね。
浄土で再び亡き人と会えることを楽しみに、今をしっかりと生きて頂きたいと思います。
スッタニパータというお経にこんな言葉があります。
『目に見えるもの、見えないもの、遠くに住むもの、近くに住むもの、すでに生まれたもの、これから生まれようと欲するもの、一切の生きとし生けるものは、幸せであれ』※出典:スッタニパータ
目に見えなくても、あなたの幸せを祈ってくれる人がいます。
遠くに住んでいても、いつもあなたのことを心配してくれる人がいます。
あなたの幸せを祈ってくれている人はきっといるのです。
あの世のご先祖様や亡きご家族も、きっとあなたの幸せを願ってくれています。
お彼岸にお墓参りをした時には、あなたもご先祖様や亡きご家族の冥福を願い手を合わせましょう。
寄稿:金剛院職員 K